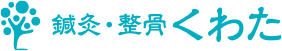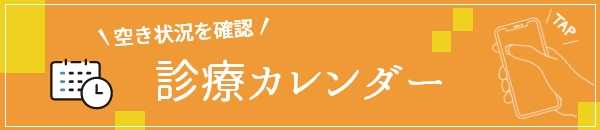足の痛み(足痛い)
足は健康の基本です
今すぐ足の痛みを解消しましょう
専門治療で足を守り 快適な生活に

こんな足の痛みでお悩みではありませんか?
- 階段の昇降がつらい
- 長時間立つことができない
- 外出する気がなくなった
- 睡眠の質が低下している
- 歩行が困難
- 動かないので体重が増えた
- 靴選びが難しい
- 精神的なストレスを感じる
足を痛めやすい方の特徴
-
- 1.スポーツや激しい運動をする人
- ランニングやジャンプなどを頻繁に行う人は、筋肉や靭帯に負担がかかり、痛みを感じやすくなります。足の過度の負荷や反復動作でも痛めやすいです。
-
- 2.立ち仕事や長時間歩く仕事をしている人
- 長時間立ちっぱなしや歩き続けることで、足に負担がかかり、痛みや疲労感が蓄積します。
-
- 3.運動不足の人
- 運動不足により足の筋力が弱くなることで、歩行や立つことに対する耐久性が下がり、痛みを感じやすくなります。
-
- 4.高齢者
- 加齢により骨や関節、筋肉の柔軟性が低下し、足の痛みを引き起こしやすくなります。また、転倒などケガのリスクも高まります。
-
- 5.肥満の人
- 体重が増えると、物理的に足への負担が増し、関節や足の裏に過度の圧力がかかって痛みが生じやすくなります。
-
- 6.ハイヒールや不適切な靴を履く人
- 足に合わない靴を長時間履くことで、足底筋膜炎や外反母趾などの痛みが引き起こされやすくなります。
足の痛みに関する主な病名と原因・症状
大腿四頭筋、ハムストリングス肉離れ
- 原因
- 急激な運動ダッシュやジャンプなど、急に方向転換したり、スピードを変えたりするような動作。
ウォーミングアップ不足十分なウォーミングアップなしに運動を始めると、筋肉が冷えた状態での運動となり、肉離れのリスクが高まります。
柔軟性の低下ハムストリングスの柔軟性が低いと、筋肉が伸ばされにくくなり、肉離れを起こしやすくなります。
筋力バランスの崩れハムストリングスと拮抗筋である大腿四頭筋の筋力バランスが崩れていると、特定の筋肉に過度の負担がかかり、肉離れのリスクが高まります。
疲労長時間の運動や過度のトレーニングによって筋肉が疲労している状態では、肉離れを起こしやすくなります。
年齢加齢に伴い、筋肉の柔軟性や回復力が低下するため、若い人に比べて肉離れを起こしやすい傾向があります。
- 症状
- 痛み筋肉を動かしたり触ったりすると、鋭い痛みを感じます。
腫れ患部が腫れ上がります。
内出血皮膚の下に青あざのような内出血が現れることがあります。
機能障害筋肉が損傷しているため、患部を動かすのが困難になったり、力が入らなくなったりします。
断裂音筋肉が断裂する際に、「ブチッ」や「バチッ」といった音が聞こえることがあります。肉離れの程度は、軽度から重度まで様々です。
軽度痛みや腫れは比較的軽度で、安静にしていれば数日で回復する場合が多いです。
中等度痛みや腫れが強く、患部を動かすのが困難になります。数週間の治療が必要になることがあります。
重度筋肉が大きく断裂しており、手術が必要になる場合もあります。
腸脛靭帯炎
- 原因
-
ランナー膝とも呼ばれ、ランニングやジャンプなど、膝を繰り返し曲げ伸ばしする運動をする人に多く見られます。太ももの外側にある腸脛靭帯が、大腿骨の外側上顆という骨と繰り返し擦れることで炎症を起こし、痛みを生じます。
オーバーユースランニングやジャンプなどの運動を長時間または高頻度で行う。
ウォーミングアップ不足十分な準備運動を行わずに運動を始める。
柔軟性の不足腸脛靭帯周辺の筋肉が硬く、柔軟性に欠けること。
体軸のズレO脚やX脚など、体の軸がずれている。
シューズの不適合クッション性が低いシューズや、自分に合わないサイズのシューズを履くこと。
地面の状態硬い地面や坂道でのランニングなど、足への負担が大きい状況での運動。
- 症状
-
膝の外側の痛み膝の外側、特に膝のお皿の少し上の部分が痛みます。
運動時の痛みランニングやジャンプなどの運動時に痛みが強くなります。
階段の上り下り時の痛み階段の上り下りや、しゃがむ動作で痛みが出ることがあります。
安静時にも痛みがある場合症状が重くなると、安静時にも痛みを感じる場合があります。
こむら返り
- 原因
- 筋肉の疲労運動や長時間の立ち仕事など、筋肉を酷使することで起こりやすくなります。
脱水汗をかいて水分が不足すると、体内の電解質バランスが崩れ、筋肉が痙攣を起こしやすくなります。
ミネラル不足カリウム、マグネシウム、カルシウムなどのミネラルが不足すると、神経伝達がうまくいかず、筋肉が痙攣を起こすことがあります。
血行不良冷えや運動不足などにより血行が悪くなると、筋肉への酸素供給が不足し、痙攣が起こりやすくなります。
神経の異常末梢神経の障害や、神経伝達物質の異常などが原因となる場合もあります。
- 症状
- 突然の痛み筋肉が強く収縮し、痛みを伴います。
筋肉の硬結痙攣を起こした筋肉が硬く、こわばります。
数秒から数分続く症状は数秒から数分続き、その後自然に治まることが多いです。
下腿三頭筋挫傷(ふくらはぎ肉離れ)
- 原因
-
急激な運動ダッシュやジャンプなど、急に方向転換したり、スピードを変えたりするような動作が原因となることが多いです。
ウォーミングアップ不足十分なウォーミングアップなしに運動を始めると、筋肉が冷えた状態での運動となり、肉離れのリスクが高まります。
柔軟性の低下ふくらはぎの柔軟性が低いと、筋肉が伸ばされにくくなり、肉離れを起こしやすくなります。
筋力バランスの崩れふくらはぎの筋肉と他の筋肉のバランスが崩れていると、特定の筋肉に過度の負担がかかり、肉離れのリスクが高まります。
疲労長時間の運動や過度のトレーニングによって筋肉が疲労している状態では、肉離れを起こしやすくなります。
年齢加齢に伴い、筋肉の柔軟性や回復力が低下するため、若い人に比べて肉離れを起こしやすい傾向があります。
- 症状
- 痛み筋肉を動かしたり触ったりすると、鋭い痛みを感じます。
腫れ患部が腫れ上がります。
内出血皮膚の下に青あざのような内出血が現れることがあります。
機能障害筋肉が損傷しているため、患部を動かすのが困難になったり、力が入らなくなったりします。
断裂音筋肉が断裂する際に、「ブチッ」や「バチッ」といった音が聞こえることがあります。
前脛骨筋炎
- 原因
-
オーバーユース長時間のランニングやウォーキング、ジャンプなどの反復運動によって、前脛骨筋に過度の負担がかかり、炎症を起こします。
運動量の急激な増加普段あまり運動をしていない人が、急に運動量を増やすと、筋肉がその負荷に耐えきれずに炎症を起こすことがあります。
不適切な靴クッション性が低い靴や、自分に合わないサイズの靴を履くことで、足への負担が増し、前脛骨筋炎を引き起こす可能性があります。
地面の状態硬い地面や坂道でのランニングなど、足への衝撃が大きい状態での運動は、前脛骨筋炎のリスクを高めます。
体軸のズレO脚やX脚など、体軸がずれていると、特定の筋肉に負担がかかりやすくなります。
- 症状
- すねの内側の痛みすねの内側、特に脛骨(すねの骨)に沿って痛みを感じます。
運動時の痛み走ったり歩いたりすると痛みが強くなります。
腫れ痛みのある部分に腫れが生じる場合があります。
圧痛痛む部分を触ると痛みが増強します。
シンスプリント(脛骨過労性骨膜炎)
シンスプリントは、すねの内側の痛みを特徴とするスポーツ障害です。正式には「脛骨過労性骨膜炎」と呼ばれ、脛骨(すねの骨)の骨膜に過度のストレスがかかり、炎症を起こす状態を指します。
- 原因
-
オーバーユース長時間、高強度のランニングやジャンプなどの反復運動を繰り返すことで、脛骨に過度のストレスがかかり、骨膜が炎症を起こします。
運動量の急激な増加きなり運動量を増やすと、筋肉や骨がその負荷に耐えきれずに損傷しやすくなります。
不適切な運動硬い地面でのランニングや、フォームの乱れ、傾斜のある路面での運動なども、シンスプリントの原因となります。
靴の不適合クッション性が低い靴や、サイズが合わない靴を履くことで、足への衝撃が大きくなり、脛骨に負担がかかります。
体軸のズレO脚やX脚など、体軸がずれていると、特定の筋肉に負担がかかりやすくなり、シンスプリントを引き起こすことがあります。
筋肉の柔軟性不足ふくらはぎや足首の柔軟性が低いと、衝撃を吸収する能力が低下し、脛骨に負担がかかります。
- 症状
-
すねの内側の痛み脛骨の内側、特に中央から下1/3にかけて、鈍痛やズキズキとした痛みを感じます。
運動時の痛み運動を始めると痛みが増し、運動後も痛みが続くことがあります。
腫れ痛みのある部分に腫れが生じる場合があります。
圧痛痛みのある部分を触ると痛みが増強します。
脛骨疲労骨折
すねの骨である脛骨に繰り返しストレスがかかることで、小さなひび割れが入り、痛みを生じる状態です
- 原因
- 過度の運動長時間、高強度のランニングやジャンプなどの反復運動を繰り返すことで、脛骨に過度のストレスがかかり、疲労骨折を起こしやすくなります。
運動量の急激な増加きなり運動量を増やすと、骨がその負荷に耐えきれずに損傷しやすくなります。
不適切な運動硬い地面でのランニングや、フォームの乱れ、傾斜のある路面での運動なども、脛骨疲労骨折の原因となります。
靴の不適合クッション性が低い靴や、サイズが合わない靴を履くことで、足への衝撃が大きくなり、脛骨に負担がかかります。
体軸のズレO脚やX脚など、体軸がずれていると、特定の筋肉に負担がかかりやすくなり、脛骨疲労骨折を引き起こすことがあります。
骨密度が低い状態女性の閉経期や加齢などにより、骨密度が低下している状態では、疲労骨折を起こしやすくなります。
栄養不足カルシウムやビタミンDなどの栄養不足は、骨を弱くし、疲労骨折のリスクを高めます。
- 症状
-
すねの痛み脛骨の内側、特に中央から下1/3にかけて、鈍痛やズキズキとした痛みを感じます。
運動時の痛み運動を始めると痛みが増し、運動後も痛みが続くことがあります。
腫れ痛みのある部分に腫れが生じる場合があります。
圧痛痛みのある部分を触ると痛みが増強します。
夜間痛夜間、寝ているときに痛みが増すことがあります。
アキレス腱炎
- 原因
-
オーバーユース長時間、高強度の運動を繰り返すことで、アキレス腱に過度の負担がかかり、炎症を起こします。
運動量の急激な増加いきなり運動量を増やすと、アキレス腱がその負荷に耐えきれずに損傷しやすくなります。
不適切な運動硬い地面でのランニングや、フォームの乱れ、傾斜のある路面での運動なども、アキレス腱炎の原因となります。
靴の不適合クッション性が低い靴や、サイズが合わない靴を履くことで、足への衝撃が大きくなり、アキレス腱に負担がかかります。
年齢加齢に伴い、アキレス腱の柔軟性が低下し、炎症を起こしやすくなります。
基礎疾患関節リウマチや痛風など、基礎疾患を持っている場合も、アキレス腱炎になりやすくなります。
- 症状
-
かかとの痛みかかとの後ろやアキレス腱の部分に痛みを感じます。
運動時の痛み運動を始めると痛みが増し、運動後も痛みが続くことがあります。
腫れ痛みのある部分に腫れが生じる場合があります。
圧痛痛みのある部分を触ると痛みが増強します。
朝起きた時の痛み朝起きた時に、アキレス腱が硬く感じられ、動き出しに痛みを伴うことがあります。
足の痛みに対する主な治療法
鍼灸・整骨くわたでは、生活に欠かせない歩行や立ち・しゃがみに支障をきたす足の痛みに対して、以下のような治療を行っています。
足の痛みの原因は人によって異なり、またその遠因となる生活スタイルもそれぞれです。このため、治療にあたっては1人ひとりの足の状態などを確認させていただき、原因を突き止めながら、その原因となる部位・患部についても合わせて治療を進めていきます。
また、何度か通院いただく場合、状態は毎回変化しますので、同じ治療を繰り返すのではなく、その時々や症状に合わせた治療をさせていただきますので、お気軽にその日の状態をご相談ください。
筋肉・骨格バランス調整

- どんな治療?
-
痛み・不調の原因は局所のみにあらず!
筋肉・骨格バランス調整法は、その人特有の癖や姿勢を崩している傾向を分析し、バランスの崩れの原因になっている部位を集中的に調整します。
今あなたが抱えている痛みは、たまたま痛みを感じやすい膝や腰に出ているだけで原因は他の部位に存在することの方が圧倒的に多いです。
同じ膝痛でも、子育てをしている方と、畑仕事をしている方と、ゴルフをしている方とでは調整ポイントは全く異なります。
ただ全身をマッサージされるだけでは効果を感じない方にもお勧めの施術です。
- どんな効果?
-
- バランスを整えることで、身体の重心が安定し、動きがスムーズになります。
- 急に痛めた場所は刺激するとかえって痛みが強くなることがありますが、痛みのある部位から離れた筋肉を調整することにより安全且つ早期の回復が見込まれます。
電気療法
プロテクノPNF

- どんな治療?
-
電気グローブを使用した治療です。
治療師が施術ポイントに狙いを定め、大きな筋肉から細かい筋肉まで日常動作では動かさない筋肉やなかなか鍛えにくい細かな筋肉へ繊細にアプローチします。
- どんな効果?
-
- 筋肉を鍛えることによって脂肪を燃焼しやすくします。
- 血液循環を改善してむくみやコリの原因を取り除いていきます。
- 姿勢改善、疼痛緩和にも効果を発揮します。
ハイボルテージ

- どんな治療?
-
高電圧電気刺激と超音波の温熱刺激をミックスさせた治療です。
治療効果の実証性が高く、オリンピック選手やプロスポーツ選手が多数使用している、痛みを取るための機器です。
刺激の到達深度が深いため、手では届かない深層の筋肉をケアすることができます。
従来の電気よりピリピリ感が少ないので、電気治療の苦手な方でも比較的安心して治療を受けていただけます。
- どんな効果?
-
- ぎっくり腰、寝違え、捻挫、突き指、関節痛、神経痛の早期回復
鍼治療

- どんな治療?
-
鍼治療はWHO(世界保健機関)が様々な症状に効果があると認める療法です。
髪の毛と同じくらいの極めて細い鍼で、ツボを刺激して不調を改善します。ホルモン、自律神経、筋肉、気、血、津液、経絡・・・
様々な身体の機能を整えますが、「東洋医学=経験医療」なので、エビデンス(医学的根拠)や可能性は未知数です。当院では鍼による感染防止・予防のため、全てディスポーザブル(使い捨て)の鍼を使用しております。
- どんな効果?
-
痛みの緩和、リラックス効果、自律神経の安定、コリの改善、血液リンパの代謝促進が挙げられますが、WHO(世界保健機関)が鍼治療の有効性を認めた疾患は以下の通りです。
-
- 運動器系
- 関節炎、リウマチ、五十肩、腰痛、腱鞘炎、むちうち、捻挫など
-
- 神経系
- 頭痛、めまい、神経痛、自律神経失調症など
-
- 循環器系
- 動悸、息切れ、高血圧症、低血圧症、動脈硬化症など
-
- 呼吸器・消化器系
- 喘息、気管支炎、便秘、下痢、胃炎など
-
- 代謝内分泌系
- 貧血、痛風、糖尿病など
-
- 婦人科系・泌尿器系
- 生理痛、月経不順、更年期障害、冷え症、膀胱炎、腎炎など
-
- 耳鼻咽喉科系・眼科系
- 中耳炎、耳鳴り、メニエール病、鼻炎、咽喉頭炎、眼精疲労など
-
- 小児科系
- 小児喘息、夜尿症、消化不良、食欲不振など
-